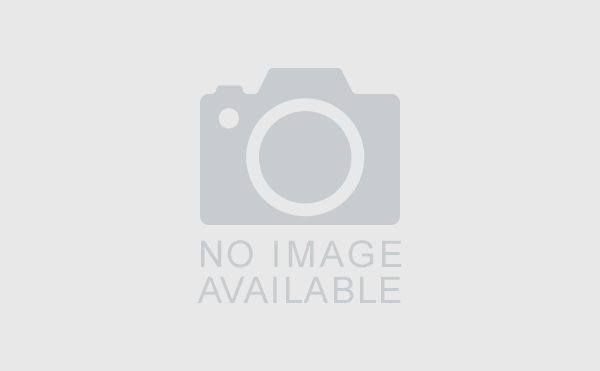この偉人はだれ?6

以下に当てはまる人物は誰でしょう?
1、生まれた年がわかっていないが寛永14~19年(1637~42年)頃といわれている
2、甲府藩主の徳川綱重、その子の綱豊(のちの6代将軍徳川家宣)に仕える
3、『塵劫記』を独学して算術を身につける
4、延宝2年、『発微算法』という著書を刊行
5、世界三大数学者のひとりに数えられている
6、江戸城内のからくり時計を直したことがあるらしい
7、中国の天元術(代数学)を元にして新しい算法、点竄術を創造した
8、円周率(円の周りの長さを出すための比率)を11桁まで求めていた
9、行列式を発見する
10、和算の大家として広く知られており、算聖と崇められている
正解は
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

関 孝和(せき たかかず)
⭐補則解説
1、生まれた場所も上野(こうずけ)藤岡説と江戸説がある
3、『塵劫記』は吉田光由が執筆した算術の教材(算数の教科書のようなもの)
4、『発微算法』は沢口一之の『古今算法記』で遺された問題に対する解答例を示したもの
5、同時代に生きたニュートン(イギリス)やライプニッツ(ドイツ)と並び称されている
6、他にも天文学や暦学、測量学も優れていたという
7、点竄術はこれまでの道具を使った算術から紙に記号などを書いて計算する方法のことで筆算のこと
8、正131072角形を用いたという。現在のところ円周率は300兆桁くらいまでわかっているらしい
9、スイスの数学者ライプニッツが1693年に導入するよりも前
略年表
寛永14~19(1637~42)年頃 内山七兵衛永明の次男として生まれる
時期不明 勘定を勤める関五郎左衛門の養子となる
寛文元(1661)年 『陽輝算法』を書写
延宝二(1674)年 『発微算法』を出版
この頃、甲府藩に仕え勘定吟味役となる
天和3(1683)年 『解伏題之法』にて行列式を導入する
貞享元(1684)年 甲府藩の検地を行う
宝永元(1704)年 藩主が将軍に就任する
宝永三(1706)年 職を辞す
宝永五(1708)年 死去
参考
大人の科学.net(https://otonanokagaku.net/issue/edo/vol3/index.html))
藤岡市HP(https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/kyoikuiinkai/bunkazaihogo/2/5/sekikouwa/1067.html)
国立国会図書館 江戸の数学(https://www.ndl.go.jp/math/s1/2.html)